スタンレー電気のものづくり
スタンレーグループの生産体制は「お客様が求める製品を必要なときに必要な数だけ生産する体制」を理想とし、全社を挙げて独自の生産革新活動「SNAP」を実践しています。徹底してムダを省くことでリードタイム短縮、コスト低減、品質向上、納期遵守を実現し、お客様の信頼と満足を高めています。間接部門においても徹底して業務効率を追求していることに加え、設備の内製化や新材料の研究など、生産技術の向上もあわせて推進しています。
SNAPとは
Stanley New Approach for higher Productivityの略で、当社流の生産革新活動の総称です。活動目的は、①お客様が満足する価値(QCD)の提供、②徹底したムダ廃除による全社的原価低減で、いかなる環境下でも利益を生み出す競争力のある会社となることです。
1997年に外部コンサルタントの指導を仰ぎながらスタートし、全社のSNAPを牽引する部署が創設されました。SNAPでは「動作・運搬のムダ」と「停滞のムダ」を2大ムダと定義し、生産現場を中心に教育と活動を進めてきました。導入初期段階では、外部コンサルタントが主催する研修に生産系の選抜社員を派遣して、内容の理解を促進するとともにノウハウを培い社内で展開を図っていましたが、現在は社内コーチによる全社員研修を行い、SNAPを浸透させるとともに生産現場だけではなく全社的な活動の推進と業務効率化を進めています。

組織体制・教育体制
全社のSNAP活動を統括し、SNAP教育や改善手法を標準化する「全社横断機能部署」を秦野製作所、「推進部署」を各生産工場に置き、連携しながら改善を進めています。「全社横断機能部署」にはプロパー社員と、社内のジョブローテーションで各部署や国内関係会社から異動してきた社員が配置されています。 「全社横断機能部署」へ異動してきた社員は2年間、他工場での改善や知識の習得を行い、元の職場に戻った後は自部署でSNAPを推進していく役割を担います。
SNAPの社内資格として「SNAPプレーヤー(実行者)」「SNAPトレーナー(指導者)」「SNAPプロフェッショナル(専門家)」の3レベル設けており、それぞれのカリキュラムに沿った研修を実施し、認定された社員に資格を授与しています。研修では、実際の生産現場におけるムダを見る目を養い、改善手法を身に付けます。生産現場だけにとどまらず、SNAPを全社的に展開し社員全員がSNAPの知識と技能を持って日々改善を進めるために、「SNAPプレーヤー(実行者) 」資格は昇格条件として人事制度にも反映され、社員全員の取得を目指しています。
また、SNAP活動報告・相互コミュニケーションの場として1年に1回「SNAP推進会」を開催し、経営層や国内外の生産拠点がオンラインで集まり、徹底したムダ廃除による改善事例の発表・ノウハウの共有・質問・相談を行っています。全社的なSNAP活動の活性化を図り、One Stanleyで原価低減へと繋げています。
-
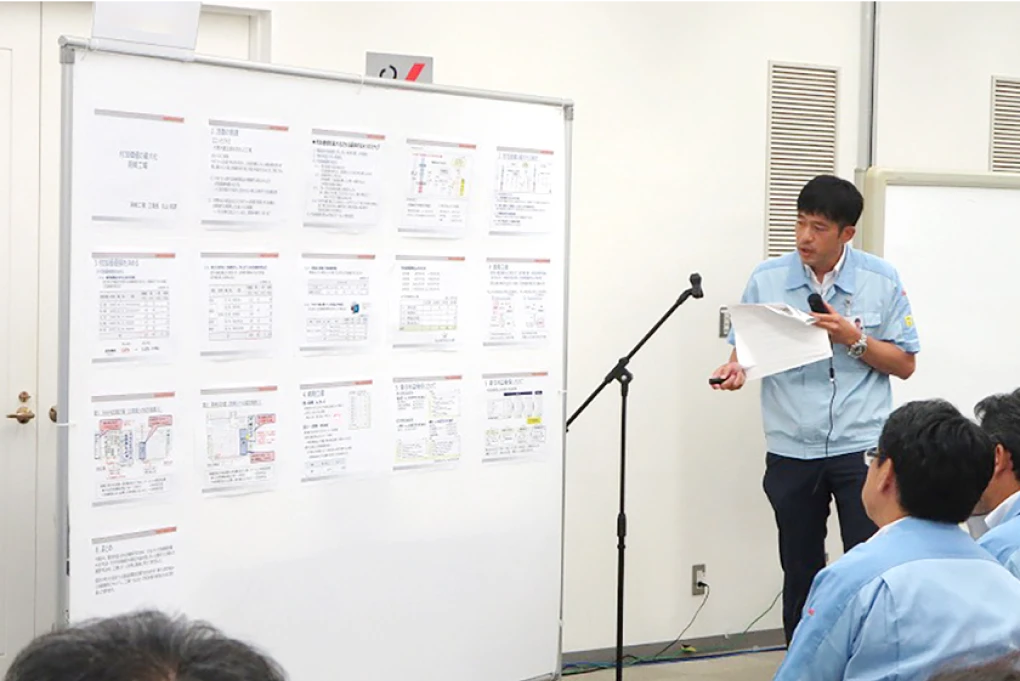
SNAP推進会の様子 -
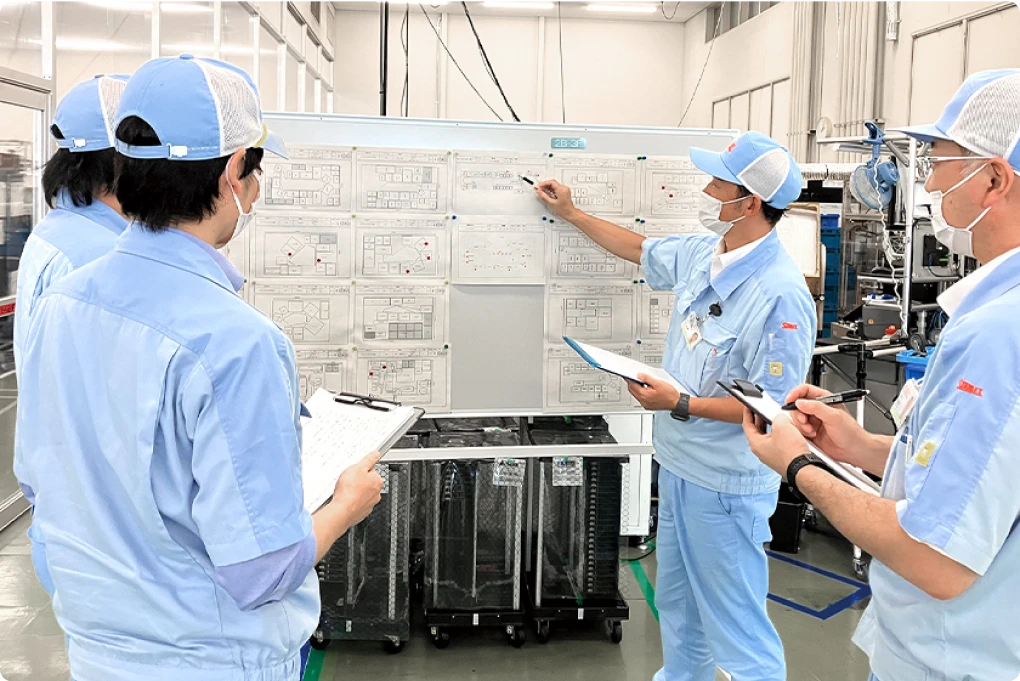
プレーヤー研修の様子
SNAP2の取り組み
2023年4月~の第Ⅷ期中期3ヶ年経営計画では、「SNAP2」として、利益の源泉である粗利益を最大化する活動を新たに加えています。自動車業界のEV化が進む中で、市場に合わせて売価下落への対応を行いながらも良い製品を提供するため、「SNAP2」では、これまでの活動の中心であった生産工程のムダ廃除による経費の削減に加えて、素材を見直すことによる「素材費低減」や「内製化」に重きをおき、取引先と一体となった原価低減活動に取り組んでいます。内製化においては、投資によりどれだけ粗利益を確保できるかを見極めた上で行うため、工場単位ではなく、グローバル全体で保有する設備全てを使い切るという視点で進め、設備操業度を上げて生産効率を高めています。
このように新たな活動を加えて生産革新活動を進化させることで、原価低減を当社グループの競争力のひとつとして磨きあげます。
