スタンレー100周年サイト

オプトエレクトロニクス企業へ
国内での地盤を着実に築いてきた当社は、1969(昭和44)年より発光ダイオード(LED)の開発に着手し、LEDの連続製造技術の開発に成功。発光効率を飛躍的に向上させ、LEDの応用分野を拡大させた。自動車産業が海外生産へとシフトする中、当社も海外生産拠点を拡大する。さらにこの時期には自動車機器でも画期的な製品を開発している。元来集光機能のみであったリフレクター(反射面)に配光制御機能を持たせたマルチリフレクターヘッドランプを開発した。これにより、従来機能部品であったヘッドランプをデザイン部品へと進化させている。1970年代から1980年代にかけて画期的な製品を次々と生み出し、卓越した技術力を背景にオプトエレクトロニクス企業として飛躍をとげていった。
CHRONOLOGY
-
1971昭和46
-
12月
発光ダイオード(赤色LED)を発売
-
-
1972昭和47
-
11月
写真用ミニストロボを発売
-
-
1973昭和48
-
4月
資本金を20億3,500万円に増資
-
緑色LEDを発売
-
8月
広島工場を開設
-
12月
オールグラスシールドビームを生産開始
-
-
1975昭和50
-
1月
黄色LEDを発売
-
2月
熊本工場を開設
-
6月
財団法人「北野生涯教育振興会」を設立
財団法人北野生涯教育振興会の設立
1975(昭和50)年6月23日、財団法人「北野生涯教育振興会」を設立。この財団法人は、青年期に病気に冒され、心ならずも勉学の道を断念せざるを得なかった北野隆春会長が、私財を提供して設立したものである。「いつでも どこでも だれでも」学べる機会を提供し、21世紀にふさわしい「生涯教育」を振興する会とした。事業内容は、生涯教育に関する助成事業、学習者に対する奨学助成事業、講演会・研修会などの事業の3つを柱とした。
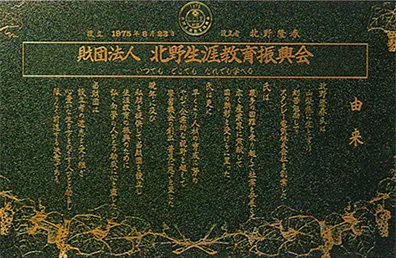
財団玄関ホールに設置されたレリーフ

創立者 北野隆春胸像
-
9月
角型4灯式メタルバックシールドビームがGM車に採用
財団法人北野生涯教育振興会の設立
1975(昭和50)年6月23日、財団法人「北野生涯教育振興会」を設立。この財団法人は、青年期に病気に冒され、心ならずも勉学の道を断念せざるを得なかった北野隆春会長が、私財を提供して設立したものである。「いつでも どこでも だれでも」学べる機会を提供し、21世紀にふさわしい「生涯教育」を振興する会とした。事業内容は、生涯教育に関する助成事業、学習者に対する奨学助成事業、講演会・研修会などの事業の3つを柱とした。
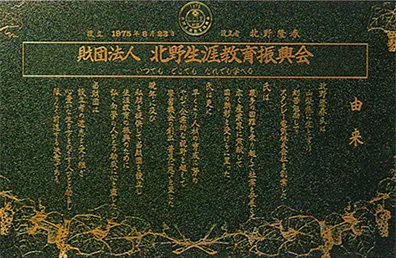
財団玄関ホールに設置されたレリーフ

創立者 北野隆春胸像
-
-
1976昭和51
-
7月
「発光ダイオード連続製造技術」が新技術開発事業団より開発成功と認定される
高輝度赤色LEDの連続製造技術の開発
当社が発光ダイオード(LED)の開発に着手したのは1969(昭和44)年のこと。LEDが世界で初めて米国のアポロ宇宙船で使われた翌年であった。それから、3年後の1972(昭和47)年10月、新技術開発事業団(現在の科学技術振興機構)より、西澤潤一東北大学教授の独創的な発明になる「発光ダイオードの連続製造技術」の実用化が当社に委託された。委託メーカーに選ばれたことは名誉であったが、この技術の実用化は困難を極めた。苦労の末、1976(昭和51)年7月には60mcd(ミリカンデラ)という世界一の明るさを持つ高輝度赤色LEDの連続製造技術の開発に成功し、1977(昭和52)年から高輝度赤色LEDの量産を開始した。
「高輝度発光ダイオードの連続製造技術の開発」は、1979(昭和54)年度の大河内記念技術賞に選出された。また、1982(昭和57)年7月には井上春成賞も受賞した。
1979(昭和54)年1月にはGaP(リン化ガリウム)の高輝度純緑色LEDを開発し、ヒット商品となった。その後、1984(昭和59)年には当社のLED開発の一つの到達点として、5,000mcd赤色、200mcd緑色、500mcd黄色の各LEDを開発した。各色とも輝度は従来品の約2倍と、これまでの業界の常識を覆す製品で、国内外の各方面から大きな注目を集めた。赤色だけであった高輝度LEDに純緑色が加わり、赤と緑が一対で使えるようになったことの意義はきわめて大きく、LED応用分野の展開に大きな前進をもたらした。
当社は"LEDのデパート"を合言葉に相次ぐ製品開発によって、音響機器、家電、カメラ、計測器、端末機器、自動販売機、玩具と用途は急速に拡大していった。
世界一の明るさを持つ高輝度赤色LED
-
10月
資本金を32億4,900万円余に増資
高輝度赤色LEDの連続製造技術の開発
当社が発光ダイオード(LED)の開発に着手したのは1969(昭和44)年のこと。LEDが世界で初めて米国のアポロ宇宙船で使われた翌年であった。それから、3年後の1972(昭和47)年10月、新技術開発事業団(現在の科学技術振興機構)より、西澤潤一東北大学教授の独創的な発明になる「発光ダイオードの連続製造技術」の実用化が当社に委託された。委託メーカーに選ばれたことは名誉であったが、この技術の実用化は困難を極めた。苦労の末、1976(昭和51)年7月には60mcd(ミリカンデラ)という世界一の明るさを持つ高輝度赤色LEDの連続製造技術の開発に成功し、1977(昭和52)年から高輝度赤色LEDの量産を開始した。
「高輝度発光ダイオードの連続製造技術の開発」は、1979(昭和54)年度の大河内記念技術賞に選出された。また、1982(昭和57)年7月には井上春成賞も受賞した。
1979(昭和54)年1月にはGaP(リン化ガリウム)の高輝度純緑色LEDを開発し、ヒット商品となった。その後、1984(昭和59)年には当社のLED開発の一つの到達点として、5,000mcd赤色、200mcd緑色、500mcd黄色の各LEDを開発した。各色とも輝度は従来品の約2倍と、これまでの業界の常識を覆す製品で、国内外の各方面から大きな注目を集めた。赤色だけであった高輝度LEDに純緑色が加わり、赤と緑が一対で使えるようになったことの意義はきわめて大きく、LED応用分野の展開に大きな前進をもたらした。
当社は"LEDのデパート"を合言葉に相次ぐ製品開発によって、音響機器、家電、カメラ、計測器、端末機器、自動販売機、玩具と用途は急速に拡大していった。
世界一の明るさを持つ高輝度赤色LED
-
-
1977昭和52
-
1月
LED数字表示器を発売
-
8月
運輸省型式指定第1号の角型4灯式シールドビーム(メタルバック)を発売
-
-
1978昭和53
-
1月
国産初のオレンジ色高輝度LEDを発売
-
3月
オールグラスシールドビーム生産累計1,000万個達成
-
4月
資本金を40億8,000万円余に増資
-
-
1979昭和54
-
1月
高輝度純緑色LEDを開発
-
9月
液晶表示素子の生産を開始
-
10月
米国に「Stanley Electric U.S. Co.,Inc.」(SUS)を設立(1981年4月にオハイオ州ロンドンに移転)
-
カラー液晶を開発
-
-
1980昭和55
-
3月
「高輝度発光ダイオード連続成長技術の開発」により第26回大河内記念技術賞を受賞

大河内記念技術賞

「高輝度発光ダイオード連続成長技術の開発」により第26回大河内記念技術賞を受賞
-
5月
「Thai Stanley Electric Co., Ltd.」(THS)を設立
-
6月
液晶バック照明専用フラット蛍光ランプを開発
-
8月
高輝度数字表示器シリーズを発売(4色)
-
第1回「スタンレーレディス・プロゴルフトーナメント」を開催
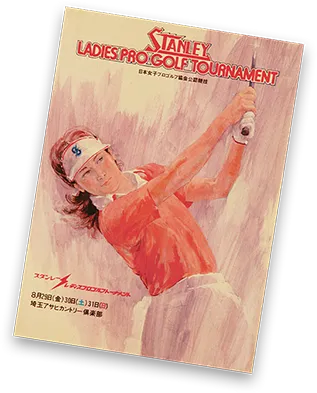
第1回「スタンレーレディス・プロゴルフトーナメント」のメインビジュアル

第1回「スタンレーレディス・プロゴルフトーナメント」優勝の吉川なよ子選手
-
10月
韓国の「三立産業㈱」と技術援助契約を締結
-

大河内記念技術賞
-

「高輝度発光ダイオード連続成長技術の開発」により第26回大河内記念技術賞を受賞
-
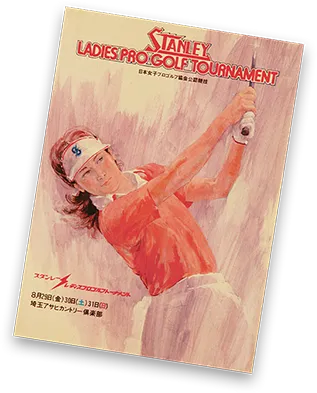
第1回「スタンレーレディス・プロゴルフトーナメント」のメインビジュアル
-

第1回「スタンレーレディス・プロゴルフトーナメント」優勝の吉川なよ子選手
-
-
1981昭和56
-
4月
角型LED使用の5連10連LEDレベルメーターを発売
-
5月
創業60周年記念総合展を開催
-
創業者 北野隆春名誉会長逝去
-
7月
オーストラリアの「HELLA(ヘラー)」と技術援助契約を締結
-
9月
岡崎製作所を開設
-
10月
面表示LED赤・緑・黄・橙各色を発売
-
-
ホンダ「エレクトロ・ジャイロケータ」にジャイロセンサーが採用

ホンダ「エレクトロ・ジャイロケータ」
-
-
1982昭和57
-
4月
高感度受光素子シリコンP型「フォトトランジスター」を発売
-
7月
「高輝度発光ダイオードの連続製造技術」により第7回井上春成賞を受賞
-
-
1983昭和58
-
3月
カラー液晶による大型表示パネルを開発
-
5月
2000mcdの高輝度赤色LEDを開発
-
9月
資本金を67億9,200万円に増資
-
10月
「㈱筑波研究コンソーシアム」が発足
-
-
1984昭和59
-
5月
インドの「LUMAX(ルマックス)」と技術援助契約締結
-
7月
5000mcd高輝度赤色LEDを開発
-
9月
筑波研究所を開設
-
12月
従来比約2倍の高輝度純緑色LED「ピュアグリーン」を発売
-
-
1985昭和60
-
6月
北野隆興社長が会長に、手島透副社長が社長に就任
-
9月
経営会議を新設
-
10月
超高出力赤外ダイオードを開発・発売
-
-
「MR (マルチリフレクター)ヘッドランプ」を開発
MRヘッドランプの開発
1985(昭和60)年、マルチリフレクター(MR)ヘッドランプの商品化に成功した。「MRヘッドランプ」とは、前面のガラス面に"レンズカットのない"ヘッドランプで、従来のレンズカットの拡散機能、配光調整機能をリフレクター(反射鏡)にもたせ、前面ガラスは素通しのカバー機能にとどめたヘッドランプである。レンズカットのないヘッドランプは世界初であり、そのリフレクターをCAD/CAMで実現したのも世界初であった。
この技術は「自由曲面ヘッドランプ」の誕生へと引き継がれていく。機能部品であったヘッドランプをデザイン部品へと進化させた歴史的な技術であり、現在もヘッドランプデザインの主流となっている。
フロントレンズに配光カットのないMR(マルチリフレクター)ヘッドランプ
-
-
1986昭和61
-
2月
1985年度「日経・年間優秀賞」の製品優秀賞を「高出力赤外LED」が受賞
-
3月
「GH型二層式大型カラー液晶表示器の開発と量産化」により第32回大河内記念技術賞を受賞
世界が注目したカラー液晶の開発と製造
液晶の研究に着手した1975(昭和50)年当時、当社は後発組に属していた。その頃主流であった液晶は2枚の偏光板で挟み込むツイストネマテック(TN)型というもので、表示色は1色に限られた。当社はカラーを鮮明に表示できる原理を開発し、一気に開発競争の先頭に躍り出ようと、日本に初めて液晶表示を紹介した東北大学の和田正信教授に共同開発を依頼した。それから6年の歳月が流れ、ついに世界で初めてカラー表示を可能にしたゲスト・ホスト(GH)二層型を開発し、本格的な生産・販売に入った。このGH二層型は多色表示が可能なことから、あらゆる情報産業分野に可能性を秘めており、特に関心を持たれたのは自動車用ディスプレイであった。このカラー液晶が発表されると世界の自動車メーカーの関心を呼び、早速、フランスのルノー公団の小型乗用車「R-11」に初採用が決まった。その後、トヨタ「コロナ」、ホンダ「アコード」のメーターパネルディスプレイとして採用され、各方面から注目を集めた。そして、1986年当社の「ゲスト・ホスト型二層式大型カラー液晶表示器の開発と量産化」は第32回(60年度)大河内記念技術賞に選ばれたのであった。第26回(54年度)のLEDとあわせ、当社のオプトエレクトロニクス製品を代表する二つが名誉ある賞を受賞した。

トヨタ「コロナ」ダッシュボード用大型カラー液晶パネル
-
8月
LEDハイマウントストップランプの量産を開始
-
宇都宮技術センターを開設
-
11月
「II Stanley Co.,Inc.」(IIS)を設立
-
-
富士フイルム㈱の初代レンズ付きフィルムカメラ「写ルンです」にストロボが採用(日本初)

「写ルンですFLASH」にストロボ採用(1987年モデル)
世界が注目したカラー液晶の開発と製造
液晶の研究に着手した1975(昭和50)年当時、当社は後発組に属していた。その頃主流であった液晶は2枚の偏光板で挟み込むツイストネマテック(TN)型というもので、表示色は1色に限られた。当社はカラーを鮮明に表示できる原理を開発し、一気に開発競争の先頭に躍り出ようと、日本に初めて液晶表示を紹介した東北大学の和田正信教授に共同開発を依頼した。それから6年の歳月が流れ、ついに世界で初めてカラー表示を可能にしたゲスト・ホスト(GH)二層型を開発し、本格的な生産・販売に入った。このGH二層型は多色表示が可能なことから、あらゆる情報産業分野に可能性を秘めており、特に関心を持たれたのは自動車用ディスプレイであった。このカラー液晶が発表されると世界の自動車メーカーの関心を呼び、早速、フランスのルノー公団の小型乗用車「R-11」に初採用が決まった。その後、トヨタ「コロナ」、ホンダ「アコード」のメーターパネルディスプレイとして採用され、各方面から注目を集めた。そして、1986年当社の「ゲスト・ホスト型二層式大型カラー液晶表示器の開発と量産化」は第32回(60年度)大河内記念技術賞に選ばれたのであった。第26回(54年度)のLEDとあわせ、当社のオプトエレクトロニクス製品を代表する二つが名誉ある賞を受賞した。

トヨタ「コロナ」ダッシュボード用大型カラー液晶パネル
-
-
1987昭和62
-
3月
LEDプリントヘッドを開発
-
4月
定年制を改正し、定年を満60歳に延長
-
9月
秦野製作所の半導体第一工場内で出火し2号館全焼
秦野製作所2号館が全焼
1987(昭和62)年9月11日、秦野製作所2号館の半導体第一工場で火災が発生した。社員は全員無事であったが、2号館全体を焼失した。出火原因は、感光体製造設備の一部装置の過熱によるものと見られた。
鎮火後すぐに「得意先のラインを止めるな」を合言葉に秦野2号館の復旧作業を進め、電装ラインは2カ月弱という奇跡的なハイスピードで生産を再開した。
全焼した2号館焼跡

火災にともなう緊急対策について指示を行う復興対策委員のメンバー

完成した秦野製作所新2号館
-
10月
米貨建新株引受権付社債(ワラント債)を発行し、ロンドン証券取引所に上場
-
12月
「Asian Stanley International Co.,Ltd.」(ASI)を設立
秦野製作所2号館が全焼
1987(昭和62)年9月11日、秦野製作所2号館の半導体第一工場で火災が発生した。社員は全員無事であったが、2号館全体を焼失した。出火原因は、感光体製造設備の一部装置の過熱によるものと見られた。
鎮火後すぐに「得意先のラインを止めるな」を合言葉に秦野2号館の復旧作業を進め、電装ラインは2カ月弱という奇跡的なハイスピードで生産を再開した。-

全焼した2号館焼跡
-

火災にともなう緊急対策について指示を行う復興対策委員のメンバー

完成した秦野製作所新2号館
-
-
1988昭和63
-
6月
情報システム6ヵ年計画(DN-6)スタート
-
7月
フランス「IDESS S.A.」(アイデス)の経営権を取得して「STANLEY-IDESS S.A.S.」(SID)と改称
-
資本金が100億円を超える
-
-
1989平成元
-
-
ホンダの「アコード」「アコードインスパイア」に「MRヘッドランプ」が採用

MRヘッドランプ初採用
ホンダ「アコード インスパイア」 -
-
1990平成2
-
4月
角型ハロゲンオールグラスシールドビームを発売
-
